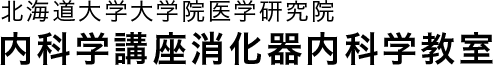Accept論文
Accept論文一覧
Human Amnion-derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation Ameliorates Liver Fibrosis in Rats.
- 受理日
Kubo K, Ohnishi S, Hosono H, Fukai M, Kameya A, Higashi R, Yamada T, Onishi R, Yamahara K, Takeda H, Sakamoto N.
- 雑誌名
Transplantation Direct
- コメント
実験開始からちょうど2年.Editorから"Congratulations on the acceptance of your manuscript"のコメントが届きました.人生初の英語論文の感想は,ただただ"嬉しい"の一言です.大西俊介先生並びに,この研究にご協力いただいた全ての先生方,学生さん達に感謝いたします.
(久保)
Endoscopic ultrasound-guided antegrade bile duct stone treatment followed by direct peroral transhepatic cholangioscopy for Roux-en-Y reconstruction.
- 受理日
Kawakami H, Kuwatani M, Kubota Y, Kawahata S, Kubo K, Kawakubo K, Sakamoto N.
- 雑誌名
Endoscopy
- コメント
久しぶりにacceptの声が聴けてホッとしています.やはりEndoscopyへのacceptはやみつきです.ここまでできるのか...,といった手技内容になっています.タイトルだけではわからないので,是非読んでみてください.
(河上)
Open-label, randomized, comparative, phase III study on effects of reducing steroid use in combination with Palonosetron.
- 受理日
Komatsu Y, Okita K, Yuki S, Furuhata T, Fukushima H, Masuko H, Kawamoto Y, Isobe H, Miyagishima T, Sasaki K, Nakamura M, Ohsaki Y, Nakajima J, Tateyama M, Eto K, Minami S, Yokoyama R, Iwanaga I, Shibuya H, Kudo M, Oba K, Takahashi Y.
- 雑誌名
Cancer Sci. 2015 Jul;106(7):891-5.
- コメント
MEC(中等度催吐性)レジメンの前投薬としてのステロイド剤の減量が可能かどうかを、HGCSGの姉妹グループであるHOPEグループで実施し、Positiveとなったものを、グループ代表者としてまとめたものがCancer Scienceにacceptとなった。札医の沖田先生を始めとして、北大、札医、旭医の各大学、関連病院などが、その垣根を越えて結集したAll北海道の研究結果であり、最新制吐剤ガイドラインの改定にも採用された。
(小松)
Peroral ultra-slim endoscopy-guided biliary drainage and stone extraction for upper gastrointestinal stenosis with a na?ve papilla (with videos)
- 受理日
Kawakami H, Kuwatani M, Kawahata S
- 雑誌名
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences
- コメント
世界初のtechniqueなのですが,Endoscopy誌にはrejectされました.JHBPSci誌に2015年1月1日に投稿して,ID number 1番をゲットしました.
新年早々何やっているの?ですよね.思ったより苦戦し,image of interestに格下げにはなりましたが,世界初のまま,のはずです.貪欲に形にすることに拘っておきます.
(河上)
The effect of a stylet on histological specimen in endoscopic ultrasound-guided fine needle tissue acquisition using 22-gauge needles: A multicenter prospective randomized controlled trial.
- 受理日
Abe Y, Kawakami H, Oba K, Hayashi T, Yasuda I, Mukai T, Isayama H, Ishiwatari H, Doi S, Nakashima M, Yamamoto N, Kuwatani M, Mitsuhashi T, Hasegawa T, Hirose Y, Yamada T, Tanaka M, Sakamoto N, for the Japan EUS-FNA stylet study Group.
- 雑誌名
Gastrointest Endosc
- コメント
阿部先生の学位論文がGIEに受理されました!Submitからacceptまで長期戦でしたが,何とかねじ込むことができました.Submitまでに同様の研究がretrospectiveとはいえ他誌に掲載され,一流誌はもちろんのことaccept自体を危ぶんでいましたので,本当に良かったです.これまでの行ったEUS-FNA関連の臨床研究から必要なこと,コツは分かったような気がします.興味のあります先生方は胆膵グループへの入隊をお待ちしています.最後に研究に参加していただきました関係者の皆様に感謝申し上げます.
(河上)
Human amnion-derived mesenchymeal stem cell transplantation ameliorates dextran sulfate sodium-induced severe colitis in rats.
- 受理日
Onishi R, Ohnishi S, Higashi R, Watari M, Yamahara K, Okubo N, Nakagawa K, Katsurada T, Suda G, Natsuizaka M, Takeda H, Sakamoto N.
- 雑誌名
Cell Transplantation
- コメント
本研究では、卵膜由来間葉系幹細胞の腸炎に対する抗炎症効果を示すことが出来ました。携わらせて頂いた研究が、このように形になりますと、とても感慨深いものがあります。今後この細胞を用いた治療が良い形で花開けばいいなと願っている次第です。研究にあたり、大西俊介先生をはじめ、たくさんの先生方にご指導いただきました。ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。また、より良い実験環境の中で研究をさせて頂きましたこと、医局の皆様方に心より感謝いたします.
(大西礼造)
Endoscopic ultrasound-guided pelvic abscess drainage using a dedicated wide, flared-end, fully covered self-expandable metallic stent.
- 受理日
Kawakami H, Kuwatani M, Kawahata S, Kubota Y, Kubo K, Kawakubo K, Sakamoto N.
- 雑誌名
Endoscopy
- コメント
やはり膿瘍ドレナージに対しては大口径ステントに限りますね.あっと言う間に治ります.NAGI stentを使用できる環境で良かったと痛感しています.Endoscopy誌に感謝を申し上げます.
(河上)
Regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumors following imatinib and sunitinib treatment: a subgroup analysis evaluating Japanese patients in the phase III GRID trial.
- 受理日
Komatsu Y, Doi T, Sawaki A, Kanda T, Yamada Y, Kuss I, Demetri GD, Nishida T.
- 雑誌名
Int J Clin Oncol.
- コメント
新規Multitarget TKIであるレゴラフェニブのGISTに対する国際共同二重盲検第三相試験GRID studyの日本人解析結果を論文化したものです。試験最中に、日本人の薬剤性肝障害による死亡例が出たために、日本人患者の組み入れがストップしてしま い症例数が少なくなった事もあり論文化にかなり苦戦しましたが、何とか論文になりました。稀少疾患であるGISTのGlobal研究に参加でき、 その日本人解析の執筆をまかせて貰えた事は大変光栄であり嬉しいことでした。サポートしてくれたグループの皆にも感謝しています。
(小松)
A guidewire-assisted biopsy technique for advancing through a biliary stricture in selective mapping biopsy.
- 受理日
Kawakami H, Kuwatani M, Abe Y, Kawahata S, Kawakubo K, Kubo K, Sakamoto N.
- 雑誌名
Endoscopy
- コメント
生検鉗子の狭窄部突破は時に苦労しますよね?日常診療で応用可能なテクニックを論文化しました.Endoscopy誌を狙って,仕留められて良かったです.
(河上)
Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer.
- 受理日
Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A, Yoshino T, Garcia-Carbonero R, Mizunuma N, Yamazaki K, Shimada Y, Tabernero J, Komatsu Y, Sobrero A, Boucher E, Peeters M, Tran B, Lenz HJ, Zaniboni A, Hochster H, Cleary JM, Prenen H, Benedetti F, Mizuguchi H, Makris L, Ito M, Ohtsu A; et al; RECOURSE Study Group.
- 雑誌名
N Engl J Med. 2015 May 14;372(20):1909-19.
- コメント
TAS102は、日本主導で開発が進んだ大腸癌のsalvage lineの抗癌剤である。Global studyとなったRECOURSE StudyでPositiveとなりNEJMにacceptとなった。基礎研究の報告を発表させて頂くなど、開発段階から協力させて頂いた事や、何より、グループ皆の努力の結果、私が代表して各国の名だたるOncologistと並んでcoauthorになれた。何より、当Gの医療が世界レベルであることが示されたわけで誇るべきものと思われる。この場を借りてグループの皆に感謝したい。
(小松)
No Benefit of Endoscopic Sphincterotomy Before Biliary Placement of Self-expandable Metal Stents for Unresectable Pancreatic Cancer.
- 受理日
- Hayashi T, Kawakami H, Osanai M, Ishiwatari H, Naruse H, Hisai H, Yanagawa N, Kaneto H, Koizumi K, Sakurai T.
- 雑誌名
- Clin Gastroenterol Hepatol
- コメント
研究タイトルは,"切除不能膵癌の胆道狭窄に対するcovered self-expandable metallic stent留置におけるendoscopic sphincterotomyの安全性と有効性に関する多施設共同無作為化比較試験"です.Quality paperへのacceptには大変な苦労がありました.盟友である,札幌医大 林先生よりコメントを頂戴していますので,宜しければ一読ください.
(河上)
札幌医大 林先生のコメント
Long-term Efficacy and Safety of Rabeprazole in Patients Taking Low-Dose Aspirin with a History of Peptic Ulcers: A phase 2/3, randomized, parallel-group, multicenter, extension clinical trial.
- 受理日
Fujishiro M, Higuchi K, Kato M, Kinoshita Y, Iwakiri R, Watanabe T, Takeuchi T, Sugisaki N, Okada Y, Ogawa H, Arakawa T, Fujimoto K
- 雑誌名
Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition
- コメント
これはラベプラゾールを用いた低用量アスピリン起因性胃・十二指腸潰瘍の再発予防の長期経過をまとめた論文です。パリエットの予防投与は2月に保険適用となりますが、その根拠になった試験の一つです。私が内視鏡判定委員を行った思い入れのある試験です。
(加藤元嗣)
Herbal medicines for the treatment of cancer chemotherapy-induced side effects.
- 受理日
Shunsuke Ohnishi and Hiroshi Takeda
- 雑誌名
Frontiers in Pharnmacology
- コメント
漢方薬は抗がん剤の副作用対策に有用と考えられており、様々な臨床試験が国内外で行われているところですが、その作用機序と臨床試験の現状をまとめました。
(大西俊介)
Intratumoral artery on contrast-enhanced computed tomography imaging: differentiating intrahepatic cholangiocarcinoma from poorly ifferentiated hepatocellular carcinoma.
- 受理日
Seiji Tsunematsu, Makoto Chuma, Toshiya Kamiyama, Noriyuki Miyamoto, Satoshi Yabusaki, Kanako Hatanaka, Tomoko Mitsuhashi, Hirofumi Kamachi, Hideki Yokoo, Tatsuhiko Kakisaka, Yousuke Tsuruga, Tatsuya Orimo, Kenji Wakayama, Jun Ito, Fumiyuki Sato, Katsumi Terashita, Masato Nakai, Yoko Tsukuda, Takuya Sho, Goki Suda, Kenichi Morikawa, Mitsuteru Natsuizaka, Mitsuru Nakanishi, Koji Ogawa,Akinobu Taketomi, Yoshihiro Matsuno, and Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Abdominal Imaging
- コメント
低分化型肝細胞癌は,肝細胞癌に典型的な画像所見を示さないことも多く,肝内胆管癌との鑑別に苦慮する場合があります.両者の画像所見を注意深く観察した結果,腫瘍内に残存する動脈走行がその鑑別に有用であるとの結果を得ました.
その結果を病理学的見地から裏付けをとり論文化したものです.論文化に際し,多くの先生方にご協力を頂きました.
この場を借りて御礼申し上げます.
Serum HER2 levels and HER2 status in tumor cells in advanced gastric cancer patients.
- 受理日
Sasaki T, Fuse N, Kuwata T, Nomura S, Kaneko K, Doi T, Yoshino T, Asano H, Ochiai A, Komatsu Y, Sakamoto N, Ohtsu A.
- 雑誌名
Jpn J Clin Oncol.
- コメント
化療Gの佐々木君が、がんセンターで苦労して研究してきた胃癌の血清Her2の研究です。卒業論文がやっとアクセプトになりました。がんセンター、大学のグループ皆の協力で成しえた仕事と思います。佐々木君は皆に感謝せねばなりませんね。でも良かったです。ご苦労様でした。
New molecular targeted therapies against advanced hepatocellular carcinoma: from molecular pathogenesis to clinical trials and future directions
- 受理日
Chuma M, Terashita K, Sakamoto N.
- 雑誌名
Hepatology Research (Review)
- コメント
A Multicenter Randomized Controlled Trial of Early Double Guidewire Cannulation to Facilitate Selective Bile Duct Cannulation: the EDUCATION study.
- 受理日
- Sasahira N, Kawakami H, Isayama H, Uchino R, Nakai Y, Ito Y, Matsubara S, Ishiwatari H, Uebayashi M, Yagioka H, Togawa O, Toda N, Sakamoto N, Kato J, Koike K.
- 雑誌名
- Endoscopy
- コメント
本邦から選択的胆管挿管に関するRCTがEndoscopyにacceptされました!Guidewire cannulationに一石を投じる研究になりました.主任研究者である,小生と同世代のバリバリの江戸っ子,笹平直樹 先生より脂っこいコメントをいただいております.大変長ーい,コメントですが,熱い魂が伝わってくると思います.是非,ご一読ください.
(河上)
公益財団法人がん研究会有明病院 消化器内科 肝胆膵担当部長 笹平 直樹先生のコメント
Huge hemothrax caused by endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for a sumucosal tumor of the gastric fornix.
- 受理日
Kawakami H, Kuwatani M, Kubo K, Kubota Y, Kawakubo K, Abe Y, Kawahata S, Homma N, Hida Y, Yoshino Y, Yagi Y, Domen H, Kaga K, Sakamoto N.
- 雑誌名
Endoscopy
- コメント
胃SMTに対するEUS-FNA後の血胸です....お恥ずかしい話ですが,世界初の偶発症です....呼吸器外科の先生方には大変お世話になりました.教授からは,"タダでは転ばないように",とのご助言をいただき...,メゲズに論文化しました.Endoscopyにacceptされて良かったです.
(河上)
Direct peroral ultra-slim endoscopy-guided biliary drainage for occluded self-expandable metallic stents in patients with cystic duct carcinoma.
- 受理日
Kawakami H, Kuwatani M, Abe Y, Kubota Y, Kawakubo K, Kubo K, Kawahata S, Sakamoto N.
- 雑誌名
Endoscopy
- コメント
Gastric outlet obstructionに対して通常の十二指腸内視鏡が挿入不能であった場合に,経鼻内視鏡によるアプローチは試みるべき方法の1つと思います.検査中のフトした思いつきをトラブルシューティングの1つの方法として論文化してみました.スピード命です.
(河上)
A unique use of a double-pigtail plastic stent: correction of kinking of the common bile duct due to a metal stent.
- 受理日
Masaki Kuwatani, Hiroshi Kawakami, Yoko Abe, Shuhei Kawahata, Kazumichi Kawakubo, Kimitoshi Kubo and Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Gut and Liver
- コメント
ちょっとした工夫をしてみたら上手くいった症例です.コスト削減にも寄与できる良い方法ではないかと
思います.今後EUS関連手技でも良い方法が生まれると良いのですが.より多くの機器開発が望まれます.
(?谷)