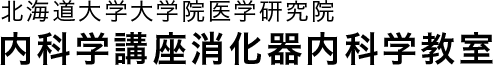Accept論文
Accept論文一覧
Serum Fibroblast Growth Factor 21 Is a Novel Biomarker of Cachexia in Chronic Liver Disease
- 受理日
Takatsugu Tanaka, Goki Suda, Masatsugu Ohara, Osamu Maehara, Tomoka Yoda, Qingjie Fu, Zijian Yang, Naohiro Yasuura, Akimitsu Meno, Takashi Sasaki, Risako Kohya, Takashi Kitagataya, Naoki Kawagishi, Masato Nakai, Takuya Sho, Shunsuke Ohnishi, Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Frontiers in Nutrition
- コメント
本論文では、慢性肝疾患患者におけるカヘキシアの診断予測因子として血清FGF21の可能性について検討しました。慢性肝疾患におけるカヘキシアは予後不良と関連することが報告されております。本研究において血清FGF21はカヘキシア群で有意に高値を示し、多変量解析では血清FGF21がカヘキシアの独立したバイオマーカーとして同定されました。その結果から血清FGF21は慢性肝疾患におけるカヘキシアの有用な予測因子であり、早期介入による予後改善に寄与する可能性が示唆されました。
本研究において研究方法や論文作成にあたり多大なるご指導・ご助言を賜りました坂本教授、須田先生、大原先生をはじめ、肝臓グループの先生方、共著いただいた全ての先生方には心より感謝申し上げます。
(田中)
Chronological change in subcutaneous adipose tissue radiodensity as a predictor of surgical outcome in patients with perihilar cholangiocarcinoma undergoing major hepatectomy
- 受理日
Ryo Sugiura, Masaki Kuwatani, Takehiro Noji, Kazumichi Kawakubo, Yoshitsugu Nakanishi, Kimitaka Tanaka, Satoshi Hirano, Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International
- コメント
近年、各種悪性疾患において皮下脂肪のCT放射線密度(SATr)の上昇(脂肪の質低下)が生命予後不良と関連すると報告されています。
今回、広範な肝切除を行った肝門部領域胆管癌において、術前待機期間中にSATrが上昇する群が術後予後が不良であることを示しています。
以前の緩和的化学療法を行った進行胆道癌での研究と合わせて、胆道癌における生命予後に皮下脂肪の質も関与しており、今後の研究が必要な状態と考えます。肝門部領域胆管癌に対して広範な肝切除を施行しデータをご提供いただきました消化器外科II 平野教授、野路教授、中西先生、田中先生には厚く御礼申し上げます。
また、研究、論文作成に関しましてご指導いただきました桒谷先生に感謝いたします。
(杉浦)
Effect of skeletal muscle mass loss on outcomes of patients with intraductal papillary mucinous neoplasm
- 受理日
Soichiro Oda, Kazumichi Kawakubo, Ryo Takagi, Katsuma Nakajima, Shoya Shiratori, Hiroki Yonemura, Shunichiro Nozawa, Ryo Sugiura, Masatsugu Ohara, Masaki Kuwatani, Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Pancreas
- コメント
学位基礎研究と並行して取り組んでいた観察研究が、Pancreas誌にacceptされました。これで、手持ちの研究内容は何とか大学院在学中に全て消化でき、とても嬉しく思っております。
IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の膵発癌リスクや予後については多くの研究がなされており、その症例数の多さから適切なfollow方法について日々議論が繰り広げられています。患者層は中高年に多く併存疾患による他因死も多いため、厳重なfollowを要する患者群とそうでない患者群の層別化が求められています。
一方、高齢者では骨格筋量が減少し、それに伴い様々な疾患の予後悪化を来たすのみならず、全身の慢性炎症による発癌リスク上昇が報告されています。
そこで今回、IPMN患者の骨格筋量を初診時点のCT画像から測定し、発癌や予後との相関について後方視的に検討しました。結果、骨格筋量減少は予後悪化だけでなく、膵発癌イベントを有意に増加させる因子であることが明らかになりました。さらに、骨格筋量が少なく併存疾患指標が少ない患者層では他因死が少なく膵発癌も多いことが分かり、より厳重な画像検査によるfollowが必要となる可能性があります。
解析症例数は700例程度で検出力がやや不足していると指摘されておりましたので、今後は前向き研究でさらに多くの症例数を集積した追加研究が必要ですが、IPMNと骨格筋量というhot topicを組み合わせた新たな視点を提供できたのではないかと考えております。本研究にあたり立案から論文執筆まで全ての段階で御指導頂きました川久保先生、統計解析のアドバイスを賜りました生物統計部門の髙木先生、日々の御指導を賜りました坂本教授、日々の臨床やデータベース構築に御協力頂きました胆膵グループの先生方に深く御礼申し上げます。
(小田)
The lever-action drill technique: a universal approach to facilitate efficient tunneling in peroral endoscopic myotomy
- 受理日
Satoshi Abiko, Yohei Nishikawa, Yuta Tamaru, Kei Ushikubo, Kohei Shigeta, Kazuki Yamamoto, Ippei Tanaka, Mayo Tanabe, Nikko Theodore Valencia Raymundo, Manabu Onimaru, Haruhiro Inoue and Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
ACG Case Reports Journal
- コメント
経口内視鏡的筋層切開術(Peroral endoscopic myotomy: POEM)における効率的なトンネリングを促進する汎用的アプローチの報告がACG Case Reports Journalに受理されました(https://doi.org/10.14309/crj.0000000000001964)。
POEMにおいて、胃食道接合部を越えて胃側へ 2 cm の範囲まで粘膜下トンネルおよび筋層切開を延長することは、標準的手技とされています。しかし、下部食道括約筋による強い抵抗や、粘膜下トンネルの屈曲により、初学者では十分にトンネルを延長できないことがあります。内視鏡用オーバーチューブ挿入時の回転操作には、軸方向の安定性と摩擦軽減という 2 つの普遍的原理が含まれており、これらが柔らかく狭い腸管腔内でのスムーズな前進を可能にしています。この原理をPOEMのトンネル内操作に応用することで、我々は Lever-Action Drill(LAD)テクニックを開発しました。ここでいう "drill" とは掘削の意味ではなく、ねじのように回転しながら前進する動作を指します。
マウスピースを支点とし、内視鏡の硬性部をレバーのように操作することで、てこの原理が働き、内視鏡先端は最小限の力で右・左方向のねじれ運動を高速に繰り返します。このねじれ運動によって摩擦が減少しつつ、軸方向の安定性が維持され、内視鏡の直線的な前進性が向上します。LAD テクニックはPOEM手技におけるトンネル作成を容易にする可能性があります。
昭和医科大学江東豊洲病院の井上晴洋教授をはじめ、同病院の先生方、内視鏡・外来・病棟スタッフの皆様、そして国内留学の機会を与えてくださった坂本先生に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
(北海道大学病院 安孫子怜史)
DNMT3B Knockdown Enhances PARP Inhibitor Sensitivity in Biliary Tract Cancer Cells via opioid growth factor receptor-Mediated Homologous Recombination Impairment
- 受理日
Soichiro Oda, Kazumichi Kawakubo, Masaki Kuwatani, Shugo Tanaka, Katsuma Nakajima, Shoya Shiratori, Hiroki Yonemura, Shunichiro Nozawa, Koji Hirata, Ryo Sugiura, Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Cancers
- コメント
学位研究として取り組んだ基礎論文をCancers誌にacceptして頂きました。
他癌種で臓器横断的に使用されるPARP阻害薬に注目し、胆道癌への応用を目指しました。他癌種の基礎研究でDNAメチル化阻害薬との併用によるPARP阻害薬効果増強が報告されていますが詳細な機序解明はされておらず、メチル化阻害薬併用や、メチル化調整因子のノックダウンによるphenotypeの確認や、網羅的なRNAシーケンスによる新規分子経路の探索を行いました。
結果的に、DNAメチル化阻害薬そのものの機序解明には至りませんでしたが、その主なターゲットであるDNMT(DNA methyltransferase)-3Bのノックダウンが、OGFR(Opioid Growth Factor Receptor)の発現亢進を介してPARP阻害薬効果増強をもたらすことを解明しました。さらに、その効果は予想外にメチル化調整ではなく転写活性の調整を介することが判明し、今後の治療開発やマーカー探索に向けた新たな知見が得られたものと考えます。
細胞実験の基礎から論文作成に至るまで全ての場面で御指導頂きました川久保和道先生、膨大なシーケンスデータ解析に当たり多大な御協力を頂きました田中秀五先生、ならびに日々の御指導御鞭撻を頂きました坂本直哉教授、胆膵グループの各先生方に厚く御礼申し上げます。
(小田)
Soluble Cluster of Differentiation 14 as a Prognostic Marker in Decompensated Cirrhosis with Water Retention
- 受理日
Masato Nakai, Masatsugu Ohara, Daisuke Yokoyama, Shoichi Kitano, Takatsugu Tanaka, Naohiro Yasuura, Akimitsu Meno, Takashi Kitagataya, Takuya Sho, Goki Suda, Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Hepatology Research
- コメント
Bacterial translocation markerとして、以前から解析を続けておりましたsoluble CD14が、体液貯留を伴う非代償性肝硬変の症例における、予後マーカーとなることをこの度Hepatology Research誌にご報告させていただきました。
sCD14は利尿剤の反応性やAKIの発症予測に有用なバイオマーカーであり、Rifaximin使用症例ではsCD14が低値の傾向を示すことも明らかにしております。この結果から、Bacterial translocationや肝内炎症が、体液貯留やAKIの治療効果不良、ひいては予後不良をもたらすこと、Rifaximin投与がこれらの治療選択肢となる可能性についてご報告ができたと考えております。
論文投稿に際して、ご指導いただきました坂本教授、Bacterial translocationマーカーの測定に関してご高配いただきました大原先生および医局の皆様、検体採取などのご協力をいただきました肝臓グループの諸先生方に深く感謝申し上げます。
(中井)
Simplified monitoring of sofosbuvir/velpatasvir in Japanese patients with chronic hepatitis C based on a retrospective analysis of a prospective multicenter cohort
- 受理日
Goki Suda1*, Masaru Baba2, Yoshiya Yamamoto3, Sonoe Yoshida3, Tetsuhito Muranaka4, Takashi Meguro5, Katsumi Terashita6, Jun Ito7, Tomoe Kobayashi8, Takaaki Izumi9, Tomofumi Takagi10, Shunichi Hosoda11, Ren Yamada11, Qingjie Fu¹, Zijian Yang¹, Daisuke Yokoyama¹, Takatsugu Tanaka¹, Akimitsu Meno¹, Naohiro Yasuura¹, Takashi Kitagataya¹, Masatsugu Ohara1, Naoki Kawagishi1,12, Masato Nakai1, Takuya Sho1, Koji Ogawa1,12, and Naoya Sakamoto1.
- 雑誌名
Scientific Reports
- コメント
このたびNORTE Study Groupで進めていたエプクルーサによる慢性C型肝炎治療の治療成績と安全性、また来院頻度を最小化した際の治療成績と安全性について検討した結果を論文と発表する事ができました。
高齢者の多い本邦のHCV感染患者においても Simplified monitoring での治療が可能となりえることを示した初めての論文化になるかとか考えます。
研究の機会を頂戴し、御指導頂きました坂本教授、御参加頂きましたNORTEStudy Groupの先生方、北大消化器内科の先生方を含め、多くの先生方のご指導のもとで論文を報告できましたこと、改めまして心より感謝申し上げます。
(須田)
Search, coagulation, and clipping with the shrink method to minimize ulcer base and prevent delayed bleeding after gastric endoscopic resection
- 受理日
Satoshi Abiko, Yukiko Okada, Kazuki Yamamoto, Yohei Nishikawa, Ippei Tanaka, Haruhiro Inoue and Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Endoscopy International Open
- コメント
Search, coagulation, and clipping with the shrink (SCC-S) methodの報告がEndoscopy International Openにacceptされました(https://doi.org/10.1055/a-2734-0575)。
胃内視鏡的粘膜下層剥離術(胃ESD)の後出血を減少させるうえで、凝固とクリッピングを併用する方法 (search, coagulation, and clipping法)は、現在多くの病院で施行されている凝固単独法 (post-ESD coagulation法)よりも有効であることが示されていますが、後出血を完全に防ぐことは出来ていません。そこで、クリッピングの際に大型のシュアクリップを使用することで、粘膜欠損部の面積を縮小できる可能性があり、それによって潰瘍治癒を促進し、後出血予防効果をさらに高めることが期待されるのではないか、と考えました。従来のSCC法で使用されていた止血クリップ(HX-610-135, Olympus Optical)と比較して、シュアクリップは経験的に把持力がより強いことが確認されており、脱落しにくい可能性があります。そのため、後出血の予防効果がより高いのではないか、と考えました。
胃ESD後の後出血を防ぐための閉鎖法はいくつか報告されていますが、全症例で閉鎖を行うことは時間とコストがかかります。胃ESDの後出血に関してのBEST-J研究によると、低リスクおよび中間リスク症例が全体の約90%を占めることから、より簡便で費用対効果の高いSCC-S法は、これらの症例群に対して合理的な選択肢となり得るかもしれません。
このSCC-S methodが、より安全な内視鏡治療の発展に寄与することを願っております。
昭和医科大学江東豊洲病院の井上晴洋教授をはじめ、同病院の先生方、内視鏡・外来・病棟スタッフの皆様、そして国内留学の機会を与えてくださった坂本先生に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
(北海道大学病院 安孫子怜史)
Balloon occlusion method using a commercially available ileus tube during endoscopic full-thickness resection: Simple solution to gas leakage
- 受理日
Haruhiro Inoue, Satoshi Abiko, Kei Ushikubo, Kazuki Yamamoto, Yohei Nishikawa, Ippei Tanaka and Naoya Sakamoto.
- 雑誌名
Endoscopy International Open
- コメント
市販のイレウス管を用いたバルーン閉鎖による内視鏡的全層切除(endoscopic full-thickness resection: EFTR)時のガスリーク対策法の報告がEndoscopy International Openに受理されました(https://doi.org/10.1055/a-2727-5056)。
胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡的全層切除(endoscopic full-thickness resection: EFTR)は低侵襲治療として注目されていますが、最大の課題のひとつは切除後の全層欠損部からのガスリークです。これにより胃内腔が虚脱し、視野の安定性や欠損閉鎖の難易度が著しく上昇します。そこで、我々は市販のイレウス管(EFTRバルーン)を全層欠損部に挿入してバルーン閉鎖法を行うことで、安定した内視鏡視野を維持しつつEFTRを完遂できた症例を今回、報告しました。
本研究は、昭和医科大学江東豊洲病院の井上晴洋教授を筆頭として、同院の上部消化管グループのメンバーとともに遂行されたものであり、責任著者として取りまとめる機会をいただきました。この場をお借りし、井上教授をはじめとする昭和医科大学江東豊洲病院の先生方、内視鏡・外来・病棟スタッフの皆様、ならびに国内留学の機会を与えてくださいました坂本先生に心より御礼申し上げます。
(北海道大学病院 安孫子怜史)
Long non-coding RNA PWRN4 associated with post-SVR hepatocellular carcinoma: a genome-wide association study
- 受理日
Suda G, Sugiyama M, Hikita H, Nishio A, Tatsumi T, Takehara T, Murakawa M, Nakagawa M, Asahina Y, Mizokami M, Kakisaka T, Sakamoto Y, Taketomi A, Miyanishi K, Ueno Y, Haga H, Maekawa S, Enomoto N, Kurosaki M, Kohjima M, Nakamuta M, Tanaka Y, Yamamoto Y, Baba M, Hanamatsu H, Furukawa JI, Ohara M, Kitagataya T, Kawagishi N, Nakai M, Sho T, Ogawa K, Sakamoto N.
- 雑誌名
Biomarker Research
- コメント
このたび、AMED坂本班で進めておりましたSVR後肝発がんに関するGWAS研究の論文が、biomarker research にアクセプトされました。
本研究では、600例を超えるC型肝炎 SVR後の症例のGWAS解析を行い、長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)PWRN4の発現と関連するSNPがSVR後の肝発がんと有意に関連すること、さらにPWRN4高発現が肝発がん(hepatocarcinogenesis)に関与し得る可能性をin vitroで示した論文となります。
研究の機会を頂戴し、御指導頂きました坂本教授、御参加頂きました全国の施設の先生方、北大消化器内科の先生方を含め、多くの先生方のご指導のもとで論文を報告できましたこと、改めまして心より感謝申し上げます。
また、本研究の成果は2025年10月1日付で 下記にて北海道大学病院より、プレスリリースを行っております。
https://www.huhp.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/20251001_press2.pdf
(須田)
The "EndoBubbloMeter": a novel orientation method to facilitate straight tunneling in peroral endoscopic myotomy
- 受理日
Satoshi Abiko, Haruhiro Inoue, Kei Ushikubo, Kazuki Yamamoto, Yohei Nishikawa, Ippei Tanaka and Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Endoscopy
- コメント
経口内視鏡的筋層切開術(POEM)における直線的トンネル作成を補助する新しい方向確認法(EndoBubbloMeter)の報告がEndoscopyのE-Videosにacceptされました(https://doi.org/10.1055/a-2686-7964)。
POEMにおいては、下部食道括約筋の2時方向、すなわち前方および後方のスリング線維(斜走筋)の間に、損傷を避けつつ内視鏡を正確に位置させることが、術後の胃食道逆流を最小限に抑え、長期的な治療効果を確保する上で極めて重要です。しかし、直線的な粘膜下トンネルを作成することは、特に初学者にとって困難な場合があります。過度なスコープの回転により、スリング線維を損傷するリスクもあります。この課題に対処するため、我々は「EndoBubbloMeter」という、水準器の原理に着想を得た新しい方向確認法を開発しました。透明キャップ内を液体で満たし、その中に発生する気泡を視認することで、トンネル剥離中にスコープの水平を維持する手助けとなります。
昭和医科大学江東豊洲病院の井上晴洋教授をはじめ、同病院の先生方、内視鏡・外来・病棟スタッフの皆様、そして国内留学の機会を与えてくださった坂本先生に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
(昭和医科大学江東豊洲病院 国内留学中 安孫子怜史)
Urinary Titin as a Non-Invasive Biomarker for Sarcopenia Sex Differences in Unresectable Digestive Malignancies: A Retrospective Cohort Study
- 受理日
Shiho Kaneko, Kazuaki Harada, Masatsugu Ohara, Shintaro Sawaguchi, Tatsuya Yokoyama, Koichi Ishida, Yasuyuki Kawamoto, Satoshi Yuki, Yoshito Komatsu, Naoya Sakamoto
- 雑誌名
International Journal of Molecular Sciences
- コメント
本研究では、近年筋損傷のバイオマーカーとして報告されている尿中Titinに関して、切除不能な消化器がん患者におけるサルコペニアの新たなバイオマーカーとしての有用性を性差に着目して検討しました。特に男性においてサルコペニア群で有意に尿中Titinが高値を示し,サルコペニア診断における有用性および性差の重要性が示唆されました。
本研究を進めるにあたり、多大なるご指導を賜りました原田先生、大原先生、化学療法グループの先生方、ご共著いただいた全ての先生方にこの場をお借りして深く感謝申し上げます。
(金子)
3-Year Overall Survival in Unresectable Hepatocellular Carcinoma Treated with Atezolizumab plus Bevacizumab
- 受理日
Masatsugu Ohara, Goki Suda, Risako Kohya, Yutaka Yasui, Kaoru Tsuchiya, Masayuki Kurosaki, Joji Tani, Shinya Maekawa, Nobuyuki Enomoto, Makoto Chuma, Manabu Morimoto, Shun Kaneko, Mina Nakagawa, Yasuhiro Asahina, Atsumasa Komori, Yuki Kugiyama, Masaru Baba, Akihisa Nakamura, Jun Ito, Ren Yamada, Shunichi Hosoda, Yoshiya Yamamoto, Sonoe Yoshida, Takuya Sho, Takashi Sasaki, Tomoka Yoda, Akimitsu Meno, Naohiro Yasuura, Qingjie Fu, Zijian Yang, Osamu Maehara, Shunsuke Ohnishi, Yoshimasa Tokuchi, Takashi Kitagataya, Naoki Kawagishi, Masato Nakai, Koji Ogawa, Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Hepatology International
- コメント
本論文は肝癌薬物療法の標準療法の一つであるアテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法(アテゾベバ療法)を受けた患者さんの3年生存率を解析した多施設共同研究となります。IMbrave150試験では、その治療法の有効性が確認され、試験は終了となったため、長期成績の報告がありませんでした。本研究では、治療開始後3年以上経過した症例のみに絞った解析を実施しています。3年生存率は約25%であり、3年生存に寄与する因子として、AFP低値、mALBI grade 1-2aであることが明らかとなりました。
論文作成にあたり、坂本教授、須田先生に多大なるご指導・ご助言を賜り、深く感謝申し上げます。また、本検討実施におきまして多大なご尽力をいただきましたNORTE study groupの先生方ならびに、全国多施設の先生方、当院肝臓Grの先生方に心より感謝申し上げます。
(大原)
Cirrhotic cardiomyopathy: Prevalence and clinical impact on liver cirrhosis outcomes
- 受理日
Takashi Kitagataya, Goki Suda, Takatsugu Tanaka, Shoichi Kitano, Naohiro Yasuura, Akimitsu Meno, Takashi Sasaki, Risako Kohya, Qingjie Fu, Shunichi Hosoda, Sonoe Yoshida, Osamu Maehara, Shunsuke Ohnishi, Masatsugu Ohara, Masato Nakai, Takuya Sho, Kosuke Nakamura, Suguru Ishizaka, Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Hepatology Research
- コメント
近年、肝硬変と他臓器との関連性が注目されています。今回私は、肝心相関の一つとして知られる肝硬変性心筋症(CCM:Cirrhotic Cardiomyopathy)という疾患に着目して研究を行いました。
CCMは2019年に診断基準が改訂され、心エコー所見により診断される疾患です。欧米では報告が散見されるものの、日本国内での有病率や肝硬変の臨床経過に与える影響についてはこれまで報告がありませんでした。そこで当院の症例を用いて後ろ向き解析を実施いたしました。
その結果、F4相当の進行線維化症例群において46.3%がCCMを有しており、CCMが非代償性イベントの独立したリスク因子であることを明らかにしました。
本研究では、心エコー所見の解釈や解析について、北海道大学大学院医学研究院循環器内科学講座の中村公亮先生、石坂傑先生にご指導をいただきました。また、須田先生や坂本先生をはじめとする消化器内科肝臓グループの先生方には、データ収集から解析、論文作成に至るまで様々な面でご指導を賜りました。ご共著いただいた全ての先生方に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。
(北潟谷)
Pre-Treatment Serum Angiopoietin-2 Predicts Prognosis and Liver Functional Reserve After Successful HCV Eradication with Sofosbuvir and Velpatasvir in Patients with HCV Related Decompensated Cirrhosis
- 受理日
Naoki Kawagishi, Goki Suda, Yuki Tahata, Hayato Hikita, Takahiro Kodama, Satoshi Mochida, Nobuyuki Enomoto, Seiichi Mawatari, Hidekatsu Kuroda, Daiki Miki, Masayuki Kurosaki, Yoichi Hiasa, Norifumi Kawada, Taro Yamashita, Hiroshi Yatsuhashi, Hitoshi Yoshiji, Naoya Kato, Taro Takami, Hisamitsu Miyaaki, Kentaro Matsuura, Yasuhiro Asahina, Yoshito Itoh, Ryosuke Tateishi, Yasunari Nakamoto, Eiji Kakazu, Shuji Terai, Masahito Shimizu, Yoshiyuki Ueno, Norio Akuta, Masatsugu Ohara, Naoya Sakamoto, Tetsuo Takehara.
- 雑誌名
Journal of Gastroenterology
- コメント
このたび、Angiopoietin-2(Ang-2)とC型非代償性肝硬変のSOF/VEL治療後の予後および肝予備能への影響を検討した論文が、Journal of Gastroenterology にアクセプトされました。
以前より、Ang-2がC型肝炎治療後の線維化に短期的・長期的に影響を与えることを報告しておりましたが、今回、AMED 竹原班の班研究の分担研究として、全国の先生方より保存血清と臨床データをご提供いただき、治療前のAng-2が非代償性肝硬変患者に対するSOF/VEL治療後の予後や肝予備能の予測マーカーとなることを発表させていただきました。
論文作成にあたり、坂本教授、須田先生には多大なるご指導・ご助言を賜り、心より感謝申し上げます。
また、貴重な検体をご提供いただきましたAMED 竹原班 代表の竹原先生、田畑先生 疋田先生をはじめ、ご協力いただいた全国の先生方に深く御礼申し上げます。
研究の機会を頂戴し、多くの先生方のご指導のもとで論文を報告できましたこと、改めまして心より感謝申し上げます。
(NTT札幌病院 川岸直樹)
Hepatocellular carcinoma with recurrent pancreatic metastasis 17 years after radical resection
- 受理日
Soichiro Oda, Kazumichi Kawakubo, Shoya Shiratori, Hiroki Yonemura, Shunichiro Nozawa, Ryo Sugiura, Masaki Kuwatani, Noriyuki Ootsuka, Shinichi Nakazato, Utano Tomaru, Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Clinical Journal of Gastroenterology
- コメント
膵腫瘍の中で他臓器癌の転移は稀ながら重要な鑑別疾患です。腎癌や肺癌からの膵転移は度々見られるものの、肝細胞癌の膵転移は少数の報告に限られています。
今回、根治切除から17年もの期間を経て、膵転移単独で再発した貴重な症例を経験したため、症例報告しました。期間が空きすぎていたため診療経過の情報が得られず考察など苦慮しましたが、何とかアクセプトを頂きました。
詳細な病理画像をご提供いただきました、病理診断科の大塚先生、外丸先生、中里先生、また論文執筆にあたり直接のご指導を賜わりました川久保先生に、深く御礼申し上げます。
(小田)
Tumor Lysis Syndrome After mFOLFOX6 Administration for Ascending Colon Cancer
- 受理日
Yuta Kano, Tetsuhito Muranaka, Wataru Saito, Yusuke Honma, Daisuke Yokoyama, Yutaro Otsuka, Soichiro Matsuda, Yunosuke Takishin, Yasuyuki Kunieda
- 雑誌名
Cureus
- コメント
上行結腸癌に対して、mFOLFOX6療法導入後に腫瘍崩壊症候群をきたした症例報告です。固形腫瘍における腫瘍崩壊症候群の中でも、mFOLFOX6療法に関連した大腸癌での症例報告はほとんどみられていませんでした。昨年度のレジデントカンファレンスで発表させていただいた症例を論文の形で報告することができました。
今回の論文作成に際し、村中先生よりたくさんのご指導を賜りました。國枝先生をはじめとした市立稚内病院の先生方にもご指導いただけたことで形にできたことは言うまでもなく、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
(市立稚内病院 加納)
Lack of association between SLFN11 expression and treatment efficacy or survival outcomes in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma
- 受理日
Takeaki Nakamura, Kanako C Hatanaka, Yasuyuki Kawamoto, Shiho Kaneko, Koichi Ishida, Kazuaki Harada, Satoshi Yuki, Yoshito Komatsu, Yutaka Hatanaka, Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
- コメント
Schlafen11というタンパク質は様々な癌腫でDNA障害型抗がん剤の効果を高めることが知られていますが、膵癌での報告はありませんでした。多くの課題に直面しながらも、学位研究の一環として試行錯誤を重ね、ひとつの成果としてまとめることができました。
研究を指導してくれた先端診断技術開発センターの畑中夫妻や、指導医である川本先生をはじめとする化学療法Grメンバーの皆さまなど、数多くの方々の支えがありました。この場を借りて心より感謝申し上げます。
(北見赤十字病院 中村赳晶)
Clinical outcomes of initial inside stenting for preoperative malignant hilar biliary obstruction in patients with jaundice
- 受理日
Ryo Sugiura, Masaki Kuwatani, Kazumichi Kawakubo, Hiroki Yonemura, Shunichiro Nozawa, Shoya Shiratori, Soichiro Oda, Kimitaka Tanaka, Satoshi Hirano, Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Surgery Today
- コメント
悪性肝門部胆道閉塞に対する術前胆道ドレナージにおいて、近年インサイドステントが広く用いています。
少数例の検討ですが、初回ERCP処置からインサイドステントを用いた症例を検討し、閉塞性黄疸症例でインサイドステントを用いると臨床的不成功となりやすいことを報告しました。
胆膵グループ先生方、手術を行なっていただいた外科先生方、ご指導頂きました桒谷先生に御礼申し上げます。
(杉浦)
Wave height fluctuations in endoscopic pressure study integrated system (EPSIS) waveforms have the potential to predict acid reflux in gastroesophageal reflux disease (with video)
- 受理日
Satoshi Abiko, Yuto Shimamura, Haruhiro Inoue, Masachika Saino, Kei Ushikubo, Miyuki Iwasaki, Kazuki Yamamoto, Yohei Nishikawa, Ippei Tanaka, Hidenori Tanaka, Mayo Tanabe, Boldbaatar Gantuya, Manabu Onimaru and Naoya Sakamoto
- 雑誌名
Digestive Endoscopy
- コメント
このたび、EPSIS(Endoscopic Pressure Study Integrated System)における波形の波高変動に関する研究論文が、Digestive Endoscopy誌にacceptされました。
本研究では、EPSISにおける波形の波高変動が、胃食道逆流症(GERD)における酸逆流の予測に有用である可能性を示しました。これにより、内視鏡を用いたGERD診断に新たな視点を提供する成果となったと考えております。
今後もEPSISの診断能をさらに高める新たな知見の蓄積が期待されます。
本研究は、留学当初に上部消化管グループのメンバーとともに構想を練り上げたテーマであり、こうして形にすることができたことを大変嬉しく思っています。
昭和医科大学江東豊洲病院の井上晴洋教授をはじめ、同病院の先生方、内視鏡・外来・病棟スタッフの皆様、メルボルン大学の島村勇人先生、そして国内留学の機会を与えてくださった坂本先生に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
(昭和医科大学江東豊洲病院 国内留学中 安孫子怜史)